|
|
![]()
魏の強さは「天の時」を支配した、その権力にこそある
後漢皇帝を擁立して勇躍する「曹操」を中心に
隻眼ながら無双の豪傑「夏侯惇」
曹操の名参謀「郭嘉」
孔明に敵する大軍師「司馬懿」…
中原の覇者に輝いた彼らの思いとは何だったのであろうか
![]()
|
曹操(そうそう) 字は孟徳。宦官の孫。頭脳明晰で思慮分別に長じた英傑。董卓の暴政を阻止するべく、諸将に呼びかけて反董卓連合を結成する。それが瓦解した後も着々と勢力を拡大。さらに後漢皇帝を擁立して確固たる勢力を築いた。呂布・袁紹など各地の豪勇を撃破して中原を手中に収め、魏建国の基礎を築いた。しかし赤壁の戦いにおいて孔明の策の前に大敗北を喫し、大陸統一の夢は打ち砕かれてしまう。彼の人物を評した一人に、こう言った者がいた。「曹操は治世では能臣になるが、乱世では姦雄となろう」と。これを聞いた曹操は怒るどころか、大いに納得したという。 |
|
曹丕(そうひ) 字は子桓。曹操と正妻・卞氏との間に生まれた。早くから曹操のもとで活躍し、曹操が没すると魏王の位に就いて跡継ぎとなった。その後、献帝に帝位の禅譲を迫って皇帝を名乗った。こうして魏を建国した彼は領内の統治に尽力し、特に陳羣の発案による九品官人法を定めたことは大きな業績となった。帝位を簒奪した彼の評判は良くないが、曹操の遺領をしっかりと統治したその手腕は評価されている。 |
|
曹叡(そうえい) 字は元仲。明帝。魏の第二代皇帝。曹丕の死後、後を継いで魏の皇帝となった。この機に乗じて蜀呉の軍勢が戦を仕掛けてきたが、呉軍に文聘、蜀軍に張コウ・曹真・司馬懿らをあたらせて防衛に専念し、これを見事防ぎきった。孔明の死後は内政に力を注ぎ、貧民に食糧援助をするなどした。死に際、曹爽と司馬懿に斉王・曹芳の補佐を頼んで亡くなったが、これが司馬懿の権力をより一層増大させる原因となった。(画・募集中) |
|
曹植(そうしょく) 字は子建。“そうち”とも。曹操の三男で曹丕の弟。曹操・曹丕・建安七子らの詩人の中で、最も傑出とされる。幼少の頃より論語や詩経などを朗読し、文才に長けていた。曹操は曹植を寵愛したため、兄の曹丕から嫌われ、曹操没後は曹丕との間に後継者争いが勃発。結果曹丕が跡継ぎの座を獲得し、以後曹植は各地に転封されることになる。兄弟が争い合うことを例え、曹丕を感動させた七歩詩は有名。(画・募集中) |
 |
夏侯惇(かこうとん) 字は元譲。曹操とは同族の出で、友人のような扱いを受けていた。曹操の旗揚げ時から付き従い、各地の戦いで武名を轟かせた。特に呂布との戦いでは敵将に片目を射抜かれるも、「これは両親から授かったもの。どうして捨てることができようか」と叫び、その矢を根こそぎ取って眼ごと喰らったという武勇伝が有名。しかしそんな豪胆な彼でも諸葛亮の計略には敵わず、博望坂で十万の兵を失うという大失態を演じた。 |
 |
夏侯淵(かこうえん) 字は妙才。夏侯惇と共に、曹操譜代の臣として活躍する。電光石火の奇襲戦を得意とし「三日で五百里、六日で千里」と賞された。しかし定軍山の戦いで法正の計略にかかり、手勢を率いて出撃したところを蜀の老将軍・黄忠に襲われ、首を討ち取られた。奇襲による戦果が多い彼だが、曹操は「指揮官たるもの慎重でなければならない」と忠告していたという。 |
|
楽進(がくしん) 字は文謙。小柄な体格ながらも豪腕の持ち主で、性格は勇猛果敢。古くから曹操に付き従い、各地を転戦して功を挙げた。濮陽での対呂布戦や張[糸肅]征討戦、沛での劉備討伐戦に獅子奮迅の活躍を見せ、特に官渡の戦いでは敵将・淳于瓊を倒すという大功を挙げた。赤壁の戦いでは、大敗した曹操を護衛する。しかしその後の濡須口の戦いで、呉将・甘寧の矢を受けて落馬、以後物語から姿を消す。正史では218年に病没している。(画・募集中) |
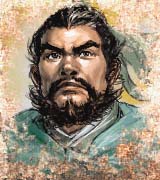 |
典韋(てんい) 字は不明。もとは農民であったが、狩りで虎を追いかけている勇姿が夏侯惇の目に留まり、曹操に推挙された。以後は都尉として曹操の護衛にあたった。しかし偽りの降伏を演じた張繍に騙され、愛用の武器を隠された上で殺されてしまった。この時典韋は立ち往生して敵を威嚇したため、この隙をついて曹操は逃げ延びることができたのであった。 |
|
于禁(うきん) 字は文則。黄巾の乱の折、鮑信の募兵に応じて出仕。その後曹操がエン州を領すると、同志と共にこれに従った。上司であった王朗の推薦により軍司馬となってからは、徐州攻略や対張[糸肅]戦などに活躍し、曹操から信頼された。軍律に照らし合わせて厳しく部下を統制し、長年曹操から可愛がられた于禁だが、樊城の曹仁を救出すべく関羽と争って敗北するとこれに降伏。曹操は、その地で忠節を曲げずに斬られた[广龍]徳と比較して「長年仕えて来た于禁が[广龍]徳の忠節にも及ばぬとは」と嘆いた。(画・募集中) |
| 許 字は仲康。身の丈八尺あまりの巨漢で剛力の持ち主。当初一族郎党と共に黄巾賊に反抗していたが、曹操が汝南に侵攻した際に典韋と賊の頭目の奪い合いになった。ここで許[ネ者]は典韋と互角に打ち合ったため、曹操は彼に仕官を勧めた。以後は曹操の片腕として各地を転戦し、特に渭水の戦いでは馬超の猛攻から曹操を救うなど活躍した。普段はぼんやりしているが、戦場では打って変わって勇猛になったため、虎痴の異名を持つ。(画・夏侯惇さん) |
|
|
李典(りてん) 字は曼成。智勇兼備の名将ながら謙虚な人物。叔父の死によりその後を継ぐことになり、以後曹操麾下の将として各地を転戦。武功を挙げて昇進を重ねていく。赤壁の戦いでは張遼や楽進と共に合肥に駐留し、呉軍の侵入を防いだ。叔父を呂布に討たれた李典は、もと呂布の臣であった張遼と折り合いが悪かった。しかし赤壁の折、張遼が私事にこだわって公事を顧みないのは恥だと述べると、李典もこれに応じて共に呉軍に当たることを誓った。(画・募集中) |
| 荀彧(じゅんいく) 字は文若。曹操の軍師。もとは袁紹に仕えていたが、これを見限って曹操の下へ帰順。以後は的確な進言で曹操の勢力拡大に貢献した。曹操は彼の功績を称え、「我が子房(張良のこと)なり」と評したという。しかし曹操の魏公就任に強く反対し、これがもとで曹操と対立。その関係が悪化し、遂には自殺を遂げてしまう。後に曹操は彼の死を悔やんだという。(画・夏侯惇さん) |
|
|
荀攸(じゅんゆう) 字は公達。荀彧の甥。荀彧の推挙で曹操に仕える。以後は官渡の戦いや赤壁の戦いに参謀として従軍し、数々の優れた策を献じた。荀彧が戦略を考案するのに秀でていたのに対し、荀攸は優秀な戦術家であり、陣中で数多くの作戦を立案した。しかし曹操の魏公即位に強く反対し、逆に恨みを買うことになった。これが原因で荀攸は憤死してしまった。 |
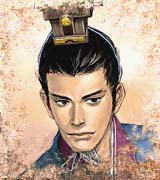 |
郭嘉(かくか) 字は奉孝。曹操の名参謀。大軍の袁紹軍を相手にして弱気になる曹操を励まし、圧倒的に不利だった曹操軍を勝利に導いた。そのため曹操から絶大な信頼を寄せられて期待されたが、惜しくも若くして病没してしまう。後に赤壁の戦いで大敗北を喫した曹操は「郭嘉が生きていたら、こんな惨めな結果にはならなかった」と声を上げて嘆いている。 |
| 程昱(ていいく) 字は仲徳。身の丈八尺の偉丈夫。荀彧の推挙で曹操の参謀となる。関羽を孤立させて曹操陣営に引き込んだり、十面埋伏の計を以て袁紹軍を壊滅させるなど、各所で優れた策を献じた。しかし許都から脱出した劉備を殺害するよう進言したり、姦計で徐庶を劉備から引き離すなど、悪印象な点も多々ある。強情な性格だったが処世術に長け、八十という長寿を保った。(画・夏侯惇さん) |
|
| 賈 字は文和。もとは董卓の娘婿である牛輔の参謀。董卓が呂布に殺されると、その残党を団結させ都を急襲するよう進言。見事呂布を長安から駆逐させた。その後は張[糸肅]に仕え、参謀として大いに活躍。曹操を相手に奇策を多用し、典韋を討ち取るなどの功績を挙げた。曹操に降った後も、離間の計を用いて韓遂と馬超の仲を裂くなど活躍。巧みな処世術で太尉にまで昇進し、天寿を全うした。(画・夏侯惇さん) |
|
 |
徐晃(じょこう) 字は公明。大斧の使い手。初め楊奉の部下だったが後に曹操に帰順。以後、各地の戦で活躍する。関羽が樊城を攻め立てた際、軍を打ち破って曹仁を助け出した。しかし対蜀戦線で孟達が蜀に寝返るのを阻止しようとした際、孟達の放った矢を受けて戦死してしまった。 |
 |
張遼(ちょうりょう) 字は文遠。丁原・董卓・呂布と仕えた主君は必ず滅ぼされるという惨めな運命を辿っていたが、曹操に帰順した後は数々の戦で大活躍。特に追い込まれた関羽を一時的に曹操に降らせたり、僅か八百の兵で十万を超える呉軍を打ち破った話などが有名。呉の人々は彼の名を聞いただけで畏怖したという。 |
| 張 字は儁艾。智勇兼備の将軍。当初は袁紹に仕えており、寧国中郎将にまで昇進した。しかし官渡の戦の折、参謀の郭図に讒言され、これを信じた袁紹に見切りをつけて曹操に降伏した。以後は各地を転戦し、特に馬超討伐戦において活躍。西方の防衛を任されるまでに至った。街亭の戦いでは馬謖を打ち破り、孔明を悩ませたが、木門道で蜀の伏兵に襲われ命を落とした。(画・夏侯惇さん) |
|
|
字は令明。馬超と共に渭水で曹操に復讐戦を挑んだが失敗。一時的に張魯の下へ降る。その後、益州に侵攻した劉備を迎撃するべく馬超が張魯の兵を借りて出陣するが、[广龍]徳は病により同行できず、これが二人の縁を断ち切る原因となってしまう。馬超は孔明の計略にかかり、劉備に投降。[广龍]徳は張魯に従い、曹操に降伏した。以後は荊州で関羽を撃退するなど活躍したが、その関羽に守っていた城を水攻めされ敗退。周倉に捕らえられ、首を刎ねられた。(画・募集中) |
 |
司馬懿(しばい) 字は仲達。当時の魏陣営で諸葛亮に匹敵する唯一の策士。諸葛亮の北伐を徹底した持久戦で阻止し、見事蜀軍を撤退させた。その後、曹爽一族の陰謀により兵権を奪われるが、見事なクーデターでこれを一蹴り。晋王朝の基盤を築き上げた。五丈原での孔明とのやり取りは有名で、諸葛亮死没を天文に読んだ司馬懿は蜀陣に総攻撃を掛けるが、逆に反撃されて兵を撤退させた。世に言う「死せる孔明、生ける仲達を走らす」である。 |